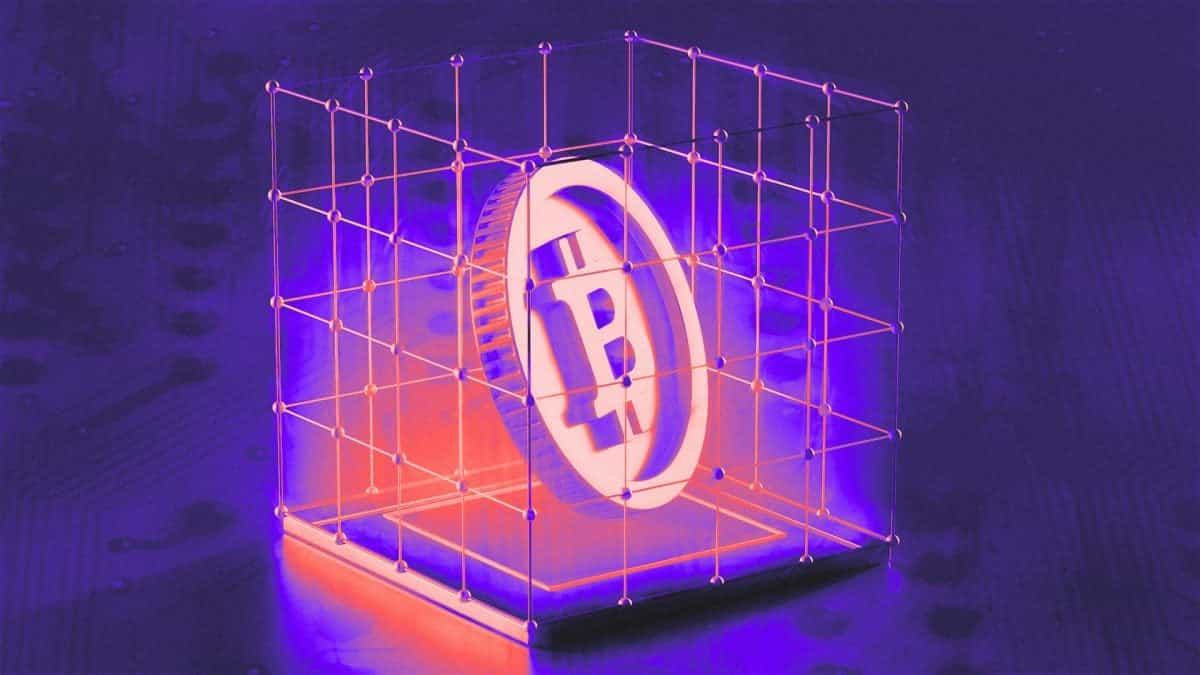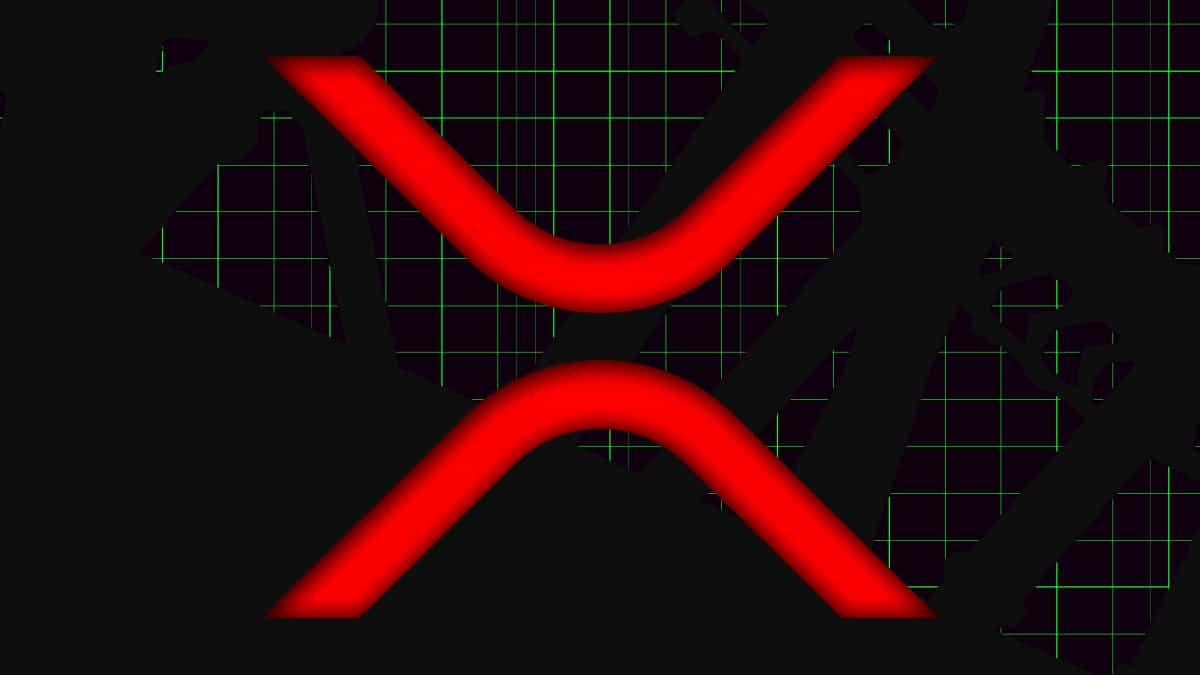2025年9月、Vitalik ButerinはEthereum Research Forumで「Rainbow Staking(レインボーステーキング)」の草案を正式に提案しました。この提案は、Ethereum Foundationの研究員Barnabé Monnotが2024年2月に提唱した初期構想を基に、Ethereumのステーキングエコシステムにおける中央集権化リスクに対応するプロトコルレベルのソリューションとして体系化されたものです。本草案は、「Heavy Staking(重ステーキング)」と「Light Staking(軽ステーキング)」を組み合わせた二層構造を提案し、検証可能遅延関数(VDF)を用いてノードのランダム選出を実現します。また、流動性プロトコルの「自己制限」条項(例:25%のシェア上限)を初めて基礎プロトコルに明記し、検証権限の分散化とエコシステムの動的バランスを促進します。この提案は、Lidoなどの流動性大手による市場支配現象に直接対応しています——現在Lidoはネットワーク全体の32%のステーキングシェアを占めています。発表から48時間以内に、SSV、Obol、Rocket Poolなどの分散型プロトコルトークンが上昇し、LDOは4.7%下落しました。これはEthereumコンセンサスレイヤーの「リバランス」への市場の高い感度を示しています。

1.Lido主導による中央集権リスクへの注目
Ethereumのステーキングエコシステムは「再中央集権化」の課題に直面しています。Lidoは32%のステーキングシェアと、38のノードオペレーターのうち上位5社が過半数の署名権を握る「二重集中」モデルにより、コンセンサスレイヤーに潜在的な脅威をもたらしています。その「1トークン1票」のガバナンスメカニズムにより、投票権の63%が上位100アドレスに集中し、年間1.8億ドルの手数料もETH保有者に十分還元されていません。さらに警戒すべきは、技術的なミス(例:ブロック漏れや重複署名)がstETHのペッグ外れや連鎖的な清算を引き起こす可能性があることです——2022年6月のstETHが6%ディスカウントされた事例は市場に強い印象を残しています。Lidoは流動性ステーキングの利便性を提供する一方で、独立ステーキング参加者(ソロステーカー)の参入を抑制し、システムリスクを高めています。単一プロトコルのステーキング比率が3割を超えると、ネットワークは51%攻撃などのセキュリティリスクにさらされやすくなり、Ethereumが目指す分散化のビジョンと相反します。
2.「Rainbow Staking」提案のコアメカニズム:階層化と制限
Vitalikが提案した「Rainbow Staking」フレームワークは、サービスのアンバンドリング(分離)によってシステムのレジリエンスを高め、独立ステーカーやプロフェッショナルオペレーターなど、異なるタイプの参加者が自分の条件に応じてサービスを選択できるように設計されています。
そのコア設計は2つのパスを含みます:
● Heavy Staking(重ステーキング):資本効率が求められるサービス向け(例:ファイナリティツール(FFG)やGasperメカニズム)。参加者はフルノードを運用し、スロットごとに署名し、スラッシングリスクを負います。プロフェッショナルなノードオペレーター向けです。
● Light Staking(軽ステーキング):検閲耐性やSybil耐性に重点を置き、抽選メカニズムでランダムに参加者を選出します。署名頻度が低く、スラッシングリスクも小さく、最低1 ETHから参加可能で一般ユーザー向けです。
このメカニズムはさらに、プロトコルシェア25%のレッドラインを導入し、これを超えると自動的にペナルティ調整が発動します。また、VDFによるランダム性強化や、分割利率による大・小プールの収益調整を通じて、Lidoのような「スーパー・プロトコル」を中立的な技術サービスチャネルへと還元し、過度な拡大を抑制することを目指します。
3.分散型プロトコルの連携対応、ステーキング市場シェア争奪
「Rainbow Staking」のコンセプトは、SSV、Obol、Rocket Pool、Pufferなどの分散型プロトコルから迅速に支持を集め、Lido以外の市場シェア獲得に積極的に動いています。
具体的な動きとしては、SSVのノード数が1週間で22%増加し、バリデータのフラグメント化プラグインをリリース。ObolはEtherFiと提携してマルチオペレーターのテストネットを推進。Rocket Poolはコミュニティ投票でミニプールの参加基準を8 ETHに引き下げ、25%のシェア自主上限を設定。Pufferは1 ETHからのノード参加とハードウェア分離技術でEthereum Foundationから助成金を獲得しました。
これらのプロジェクトは共通して「非カストディ」と「フラグメント化」の特徴を強調し、独立ステーカーの参加機会を拡大し、LST(流動性ステーキングトークン)の信頼性向上を目指しています。二次市場で関連トークンの価格変動も、分散型代替案への投資家の期待を反映しています。

4. 結論:分散化に「終局」はなく、動的バランスのみが存在する
Lidoも受け身ではなく、最近ではstETHとLDOの二重ガバナンスメカニズムの導入、手数料率の7%への引き下げ、2万ETHの分散型リザーブ設立、「コミュニティステーキングモジュール」計画によるノードオペレーターの100社超への拡大などの施策を講じています。しかし、「Rainbow Staking」の実現には、ガバナンス面での意見の相違(例:a16z、Paradigmなどの投資機関が開発者会議で持つ影響力)や、ハードフォークの実施スケジュールなど、多くの課題が残っています。
もし提案が2026年のPectraアップグレードとともに順調に実施されれば、Ethereumステーキング市場の集中度は今後3年でCR5<45%まで低下し、Lidoのシェアは22%-25%に縮小、ネットワーク全体の年率リターンは3.2%-4.8%で推移すると予想されます。
最終的に、分散化は一度きりで達成できる究極の状態ではなく、技術的メカニズム、経済的インセンティブ、ガバナンス文化の間で絶えず調整・進化し続ける動的なプロセスです。最終的に、分散化は一度きりで達成できる究極の状態ではなく、技術的メカニズム、経済的インセンティブ、ガバナンス文化の間で絶えず調整・進化し続ける動的なプロセスです。
ぜひ私たちのコミュニティに参加し、一緒に議論し、共に強くなりましょう!