日本最大の預金保有銀行がステーブルコインに類似したものを発行へ
Japan Post Bankは2026年にDCJPYを導入する予定であり、日本におけるブロックチェーン導入の大きな一歩となります。この取り組みは証券決済を強化し、ステーブルコインとは異なる特徴を持ち、フィンテック競争が激化する中で相互運用性の課題も浮き彫りにしています。
Japan Post Bankは、セキュリティトークンの決済にDCJPYを活用したデジタル預金通貨の導入を計画しています。この取り組みは、金融インフラの効率化を図り、日本経済全体での幅広い応用を模索することを目的としています。
Nikkeiによると、Japan Post Bankは2026年までに口座保有者向けにデジタル預金通貨を導入する準備を進めています。
DCJPYの為替レートは1円にペッグ
この取り組みでは、Internet Initiative Japan(IIJ)グループ傘下のDeCurret DCPが開発したDCJPYを利用し、デジタル証券やその他の金融商品を決済します。また、地方自治体の補助金支払いにもこのシステムの活用を検討しています。
計画されているDCJPYシステムでは、預金者が専用口座を既存の貯蓄口座に連携し、残高を円と1対1のレートで交換できるようになります。日本最大の預金機関であるJapan Post Bankは、約1億2000万口座を保有し、預金総額は約1.36兆ドルにのぼります。これにより、DCJPY発行の潜在的な基盤が大きくなり、日本のデジタル資産エコシステム内での通貨の存在感が大幅に拡大する可能性があります。
最近認可されたJPYCのようなステーブルコインとは異なり、DCJPYは規制当局が「トークン化預金」と定義するものです。ステーブルコインは一般的にパブリックブロックチェーン上で発行され、グローバルにアクセス可能ですが、トークン化預金は規制された金融機関が管理する許可制ブロックチェーン上でのみ発行されます。
DeCurret DCPは、DeCurret Holdingsの子会社であり、IIJが最大株主として支援しています。DCJPYは正式に1年前、昨年8月にローンチされました。同年9月には、DeCurretがDCJPY事業基盤強化のために約63.5億円を調達しました。
今後の相互運用性の課題
当初、Japan Post BankはDCJPYを主にセキュリティトークンの決済に利用する予定です。しかし、規制や安全性の観点から、セキュリティトークンは現在、許可制ブロックチェーン上で発行されているため、プラットフォーム間の相互運用性が依然として重要な課題となっています。
日本のステーブルコインに関する規制の進展は2025年に加速しており、今年初めにはJPYCが国内初のステーブルコインライセンスを取得しました。Japan Post Bankがブロックチェーンベースの決済に参入することで、国内最大手の金融機関が分散型台帳技術をより本格的に取り入れ始めています。アナリストは、導入が拡大するにつれて、日本のフィンテック業界での競争が激化する可能性があると指摘しています。
免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
こちらもいかがですか?
SEC議長アトキンス、「イノベーション免除」を推進、年末までに暗号資産製品の迅速承認を目指す
火曜日、Fox Businessのインタビューで、SEC会長のPaul Atkinsは、2025年末までにイノベーション免除を導入したいと述べました。Atkinsは以前、企業が迅速にオンチェーンの製品やサービスを市場に投入できるように、「イノベーション免除」を検討するようスタッフに指示したと語っています。
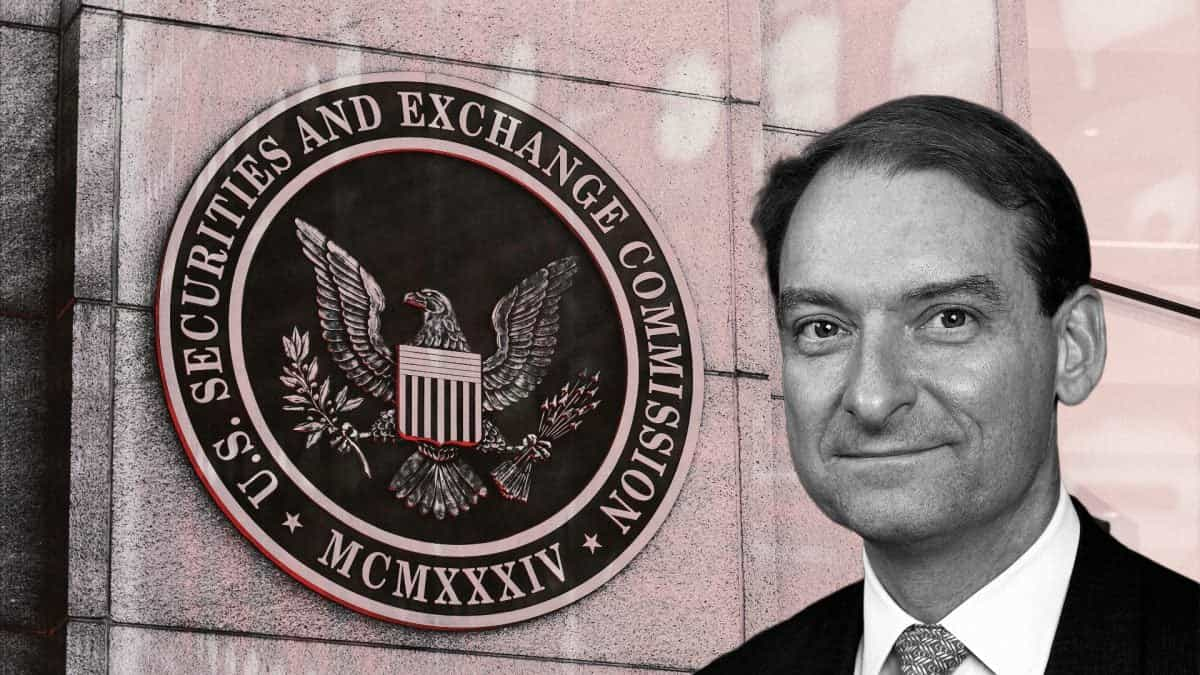
Fnalityが1億3600万ドルのシリーズC資金調達を実施、トークン化市場向けの決済インフラ拡大へ
Fnalityは、主要な銀行や資産運用会社が主導するシリーズCラウンドで1億3,600万ドルを調達し、決済ネットワークの拡大を目指しています。英国のブロックチェーン決済開発企業であるFnalityは、2019年以降、事業資金として総額2億8,000万ドル以上を調達しています。
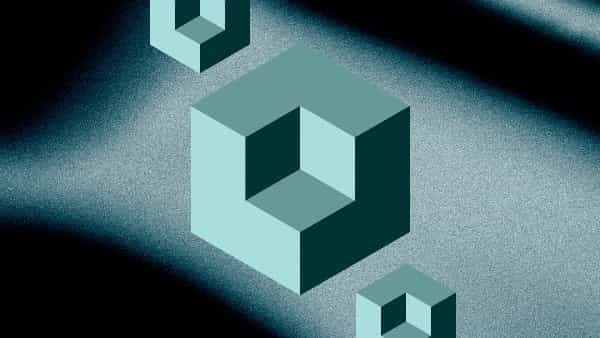
アーサー・ヘイズは、bitcoinが2028年までに340万ドルに達する可能性があると予測
Smarter Web Companyが55 BTCを購入、現在2,525 Bitcoinを保有
